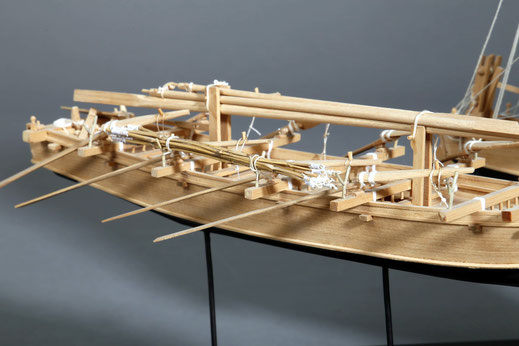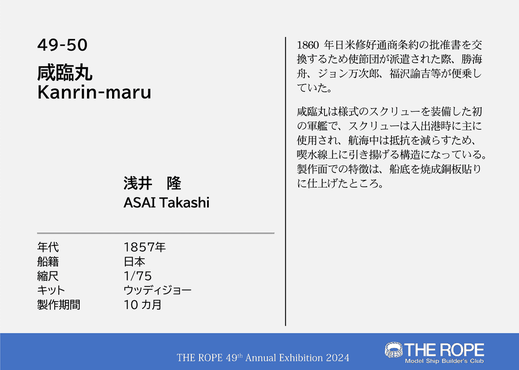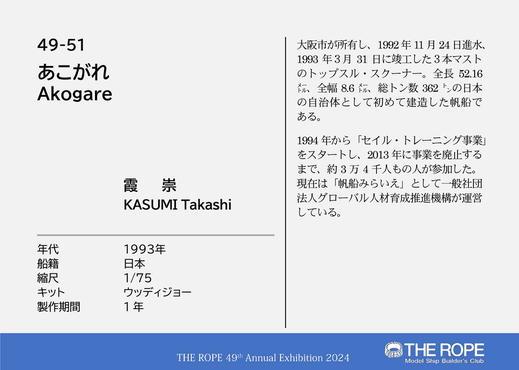〈特別展示〉日本の船
49-09
明治丸(初代)
赤道達也
| 年代 | 1874年 |
| 船籍 | 日本 |
| 縮尺 | 1/96 |
| キット | 自作 |
| 製作期間 | 2年 |
1874年(明治7年)、明治政府が英国に発注した灯台補給船。全長70㍍弱、約1030㌧の鉄船。1876年(明治9年)、明治天皇が北海道・東北地方巡行の際に、函館から乗艦されて7月20日に横浜に帰港したことを記念して、1941年にこの日を『海の記念日』(現在の『海の日』)に制定した。1897年、東京商船学校(現東京海洋大学)に移管されて練習船となった。1964年、越中島の大学構内に固定し、現存する唯一の鉄船として国の重要文化財に指定された。
キットは不明な部分が多く、実物の写真を数多く撮って参考にした。
日本資本主義の父とも称される渋沢栄一を主人公に幕末から明治までを描くNHK-TVの大河ドラマ『晴天を衝け』(2021年11月放送) で、この模型がクローズアップされて使われた。
49-11
土佐和船20尺チヌ(黒鯛)釣り船
関口正巳
| 年代 | 現代 |
| 船籍 | 日本 |
| 縮尺 | 1/10 |
| キット | サーマル工房 |
| 製作期間 | 5週 |
湾内・沿岸部での漁ができるように耐波性を重視した和船で、釣り舟には欠かせないカンコという生簀を装備している。高知ではチヌ釣りに使用され、左手で櫓を操作し、右手に釣り竿を持ち、巧みに船を操作しながら釣りをするハイカラ釣りという伝統的な漁法が用いられている。
模型は地元高知産の杉材を使用したキットで、レーザー加工の焦げった部分をサンディングするだけで容易に組み立てられる非常に作りやすいキットといえる。組み立て説明書では瞬間接着剤での組み立てを説明しているが、感想としては「木工ボンド」の使用をお勧めする。
49-12
遣唐使船
高成田潔
| 年代 | 8世紀頃 |
| 船籍 | 日本(大和国) |
| 縮尺 | 1/60 |
| キット | 自作 |
| 製作期間 | 8か月 |
奈良~平安時代にかけて、唐の文化や制度、仏教を学ぶために派遣された遣唐使を乗せた船。894年廃止までのおよそ200年間に百数十人を乗せ、十数回送られた。全長約30㍍、幅7~8㍍、竹で編んだ帆に2本の帆柱を持つ大型構造船で、舷側に櫓を装備し、帆走と櫓走とを併用した。日本の帆船史上、最初の外洋帆船といえる。
絵巻物の不確かな挿絵程度の資料しかなく不明な点が多いが、海洋考古学などの研究から、奈良県平城京跡歴史公園や広島県呉市の倉橋島に復元船が作られ、それらを参考に製作した。甲板上は寺院建築の要素もあり、今まで経験したことのない製作工程を楽しめた。
49-14
菱垣廻船「浪華丸」
田中武敏
| 年代 | 18世紀 |
| 船籍 | 日本 |
| 縮尺 | 1/100 |
| キット | 自作 |
| 製作期間 | 2年 |
1.江戸時代に、大阪-江戸間の物流を支えた純日本式構造の貨物船。十組問屋が自らの船にトレードマークの「菱垣」をつけたことから菱垣廻船と呼ばれる。モデルは「なにわの海の時空館」の「浪華丸」。
2.和船の特徴は、❶沿岸輸送が主目的、❷構造はろっ骨がなく外板は大厚板を大釘で止めた構造、❹水密性に弱点。
3.和船の内部構造をご覧いただきたい。また動的な様子を再現するために水主(フィギュア)を配した。船台は海の波をデフォルメして表現し、回転するように工夫している。
4.ウッディジョーが「菱垣廻船」をキット化するに際しては、企画協力をした。
49-18
肥後藩 海御座船「泰寶丸」
田中武敏
| 年代 | 18-19世紀 |
| 船籍 | 日本 |
| 縮尺 | 1/50 |
| キット | 自作 |
| 製作期間 | 1年 |
1.海御座船は、主に西日本の諸大名の参勤交代時に、瀬戸内海の輸送手段として活躍。
2.泰寶丸は、波奈之丸と共に肥後藩の海御座船で、全長約30㍍、64挺小艪を持つ。御座船には数十隻の共船が一緒に随行した。
3.航路は、熊本 (陸路)→大分 (海御座船) →大阪 (川御座船) →伏見 (陸路東海道) →江戸。旅程は約40日を要した。
4.船の科学館や熊本博物館などからの資料を基に、図面は平面図と側面図から断面図を起し、また屋形部分は現存する「波奈之丸」の屋形を参考にした。使用木材はヒノキ、塗装は水性工芸うるし(数回の重ね塗り)を使用。
49-19
川御座船
田中武敏
| 年代 | 18世紀 | |
| 船籍 | 日本 | |
| 縮尺 | 1/50 | |
| キット | 自作 | |
| 製作期間 | 1年 |
1.江戸時代に将軍や大名が使用した川御座船は、海御座船と違って軍船としての機能はない。この船は大阪の淀川で参勤交代・朝鮮通信使・琉球使節の送迎に使用された。そのために船体、屋形ともに豪華に装飾されていた。
2.船の構造は、平底船(ひらたぶね)で、左右の舷側の板を先端で接合した二枚水押(みよし)の船首をした船。大型の川船にしては珍しく帆の設備がなく、船を進めるには櫓と棹を使用した。
3.船の科学館、神戸市文化財課、国立国会図書館などの諸資料をベースにして、不明な箇所は類推して製作した。木材はヒノキ、塗装は水性工芸うるし、ふすま絵などはPCデータ、舳は金箔を使用。
49-21
小早型鰹釣り船
岩本和明
| 年代 | 江戸時代から明治中期 | |
| 船籍 | 日本 | |
| 縮尺 | 1/48 | |
| キット | 自作 | |
| 製作期間 | 6カ月 |
船足の速い小早船(軍船)をもとにして江戸時代から明治まで使われた焼津の鰹漁船。明治時代には15~16人の漁師が乗って遠州沖や伊豆近海を漁場として活躍した。徳川家康が焼津から久能まで魚船で渡ることになり焼津の業船が警護に随伴したが天候が悪くなり、いくら漕いでも進むことができなくなった。このため、江戸時代は漁船の櫓は7本までと決められていたが、特別に八丁櫓を許されたといういわれがある。
自作するにあたって、ウッディジョーのキットの図面、焼津の大覚寺全珠院に奉納された実船、焼津漁業資料館と焼津歴史民俗資料館の模型を参考にした。帆走と櫓走の二種類の模型を対にして製作したが、竜骨のない和船なので床の一部を空けて中が見えるようにした。解体した実家の障子枠に使われていたヒノキを製材して材料にしている。